

萩原朔太郎は、その作品によって随分印象が違う。
「月に吠える」「青猫」の口語自由詩にみられる病的なまでのイメージの繊細さ。
ボードレールのような都会や群衆を歌った詩。
「氷島」の激しい文語調による漂泊者の悲痛な詩。
小説「猫町」のような幻想とユーモア。
ニーチェを連想させるアフォリズム。
徹底した二元論に捕らわれた(あるいは引き裂かれた)詩論や文明論。
音楽や写真、映画など当時のモダンな趣味に関するエッセイ、などなど。
だから朔太郎論のテーマは、論者の好みによって、口語自由詩時代の詩語やイメージだけを重視したものや
「氷島」と日本近代についてだけ論じたものとに分かれる傾向がある。
それら作風の違う作品を時間軸によって繋げたかった。
それは、取りも直さず朔太郎の生きた時代を考えることでもあり、
当然それに繋がる私たちの生きる時代、今を考えることにもなった。
土田 和夫(ねこギター)
|
|
|
萩原朔太郎論
|
|
|
|
|
(1)テーマ 萩原朔太郎の作品を読んで、まず気付くのは、彼の故郷に対する愛憎である。 (2)方法 朔太郎は詩人であるが、アフォリズム、評論、小説、エッセイ等も数多く書いており(特に晩年期)、それらも軽視せず扱っていく。しかし論を進める前に、便宜上詩を中心に四つの時期に分けてみたい。 |
|
|
|
萩原朔太郎論
|
 |
|
|
|
(1)田舎への嫌悪 第一章は、「はじめに」で述べたように東京移住(大正十二年二月)以前の詩作品を中心にみていく。 この他にも田舎への嫌悪は、『月に吠える』の「孤独」「さびしい人格」、『青猫』の「厭らしい景物」「白い牡鶏」、『蝶を夢む』の「まづしい展望」「農夫」に見ることが出来る。アフォリズムの方では、『新しき欲情』の「田園居住者から」「荒寥たる地方での会話」、『虚妄の正義』の「田舎と都会」等がある。また少し時期はずれるが、東京移住まもない頃、郷土前橋と田舎に関する文章をいくつも発表している。「或る詩人の生活記録」「田舎に帰りて」「秋日漫談 私の郷土」「田舎居住者から」「田舎から都会へ」等がある。 しかし、どうなのだろう。はたして実際の前橋は、朔太郎のいうような土地なのだろうか。『伝記萩原朔太郎』(以下『伝記』と略す)の著者嶋岡晨氏は、同書上巻第二章故郷において次のように述べている。 (2)都会への憧憬 朔太郎の求めるものは、中途半端な「前橋なり」のものではなくて、もっと極端なものであった。朔太郎が郷土前橋を「田舎」として嫌悪することは、その対立項である「都会」が憧憬の対象になることであった。つまり、田舎と都会という両極の一方を前橋に押し付け、もう一方の極、都会に自分の理想郷を見付けようとしたのだ。次の詩は、『月に吠える』の中の「さびしい人格」である。 |
|
|
|
萩原朔太郎論
|
 |
|
|
|
(1)『純情小曲集』 朔太郎が東京移住(大正十四年二月)間もない頃に刊行した第四詩集『純情小曲集』は、前編と後編に分かれる。 やさしい純情ちた過去の日々を記念するため、このうすい葉っぱのやうな詩集をだすことにした。(中略)
(2)「青猫以後」 第五詩集『萩原朔太郎詩集』(昭和三年刊)に収録された「青猫以後」の詩編は、大正十二年から昭和三年、朔太郎三十八歳から四十二歳にかけて発表されたもので、「郷土望景詩」と時期的に重なる。だがここで注目すべきは、実際の東京生活から生まれた「鴉」「大井町」「空家の晩食」等の作品が収められていることである。 どこにも人間の屑がむらがり |
|
|
|
萩原朔太郎論
|
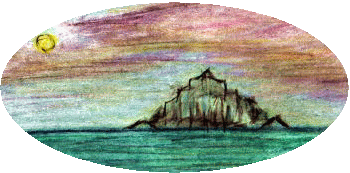 |
|
|
|
(1)『氷島』 第六詩集『氷島』は、昭和十年六月に刊行された。収録作品二十五編のうち四編は、「郷土望景詩」からの再録。二十一編の新作品は、大正十五年四月から昭和八年六月にかけて各種の雑誌に発表されたもの。朔太郎四十一歳から四十八歳の時である。 (2)『詩の原理』 朔太郎にとって実生活の事件が、漂泊者の認識を決定的にしたと言えるかも知れない。しかし、それ以前に自らの生きる時代を過渡期と捉えていたことが、この認識の背後にあったと考える。その過渡期の時代認識は、ちょうど稲子夫人の所業で家庭内が紛雑化していた頃の昭和三年十二月に刊行した『詩の原理』において為されていた。 |
|
|
|
萩原朔太郎論
|
 |
|
|
|
(1)伝統的なるもの 『氷島』以後の言わば晩年期に於いては、詩作品は数編の散文詩を除いて殆ど発表しなくなる。 そのかわり詩論、歌論、文明批評等のエッセイは精力的に発表し続ける。 昭和十年から昭和十五年の間に十二冊の著書と一冊のアンソロジーを刊行している。それは次の通りである。 かつて僕は、旧著「詩の原理」で巻尾に結論して一つの宿題を提出した。
それは、「島國日本か?世界日本か?」と標題した反問だった。そしてこの問題は、今日まで尚ほ依然として未解決に残されている。 そして巻尾「詩の未来」に、その問題を次のように述べる。
こう詩の未来を語る朔太郎なのだが、彼自身にはもうその未来に向かって行く力と時間は残されていない。 新しい日本語を発見しようとして、絶望的に悶え悩んだあげくの果て、
遂に古き日本語の文章語に帰ってしまった僕は、詩人としての文化的使命を廃棄したやうなものであった。
僕は老いた。望むらくは、新人出でて、僕の過去の敗北した至難の道を有為に新しく開拓して進まんことを。 この頃から朔太郎の文章には、過去の完成された美、伝統的なるもの(和歌、俳句、能など)に関するものが多く登場する。
『廊下と室房』の「和歌と恋愛」「悲恋の歌人式子内親王」や『詩人の使命』の「俳句について」「蕪村俳句の再認識について」等である。 それは、時間の彼岸に実在している。彼の故郷に対する「郷愁」であり、昔々しきりに思ふ、子守唄の哀切な思慕であった。 また付録「芭蕉私見」に於ける芭蕉の句の解釈も「枯枝に止った一羽の鳥は、彼の心の影像であり(中略)漂泊者の黒い凍りついたイメージだった」 であり、「魂の家郷を持たない芭蕉」であった。これらの主張は、取りも直さず朔太郎自身の投影であり、自らの心象風景を見ているのである。 (2)日本的なるもの このように先人の文学者に対して漂泊者の影を求めた朔太郎であったが、それは同時代の永井荷風にも向けられる。 (永井荷風の『墨東奇譚』は)老いてその家郷を持たない一文学者が、赤裸に自己の生活を告白し、
寄るべなき漂泊者の寂しさを、綿々纓々として叙べ訴へた抒情詩であり、併せて一の魂の哀切なる懺悔録である。/
我等の時代の日本人は、老いたる者も若き者も、共にその安住すべき家郷を持たないことで、現実の悲しみを共にしている。(中略)すべての人は家郷の「日本」さへ見失っているのである。 ここでは、単に個人としての共感だけでなく、同時代を生きる者としての共感を述べている。 過渡期に於いては、人は家郷を持ち得ない漂泊者である。
何も家郷を持たないのは自分だけでなく、寧ろ近代日本の状況そのものが「日本」を見失っていると朔太郎は考えた。 少し以前まで、西洋は僕等にとって故郷であった。
昔浦島がその魂の故郷を求めようとして、海の向うに、西洋という蜃気楼をイメージした。だがその蜃気楼は、今日もはや幻想から消えてしまった。 ここで言えることは、朔太郎が以前憧憬した都会とは、実は西洋のことであり、日本近代化の夢だったのだ。そして敗北し、再び古い日本へ回帰したということである。 むしろ西洋的なる知性の故に、僕等は新日本を創設することの使命を感ずる。(中略)
今や再度我々は、西洋からの知性によって、日本の失われた青春を回復し、古い大唐に代るべき、日本の世界的新文化を建設しようと意志しているのだ。 ここの文章からすると、決して日本的なるものへ全面的に回帰した訳ではない。まだ西洋を捨てていないからだ。 寧ろ西洋の知性によって日本の世界的建設を意志すると言うのだ。(大仰な文章が鼻に付くけれど)それなのに何故「日本への回帰」なのだろうか。 日本的なるものへの回帰!それは僕等詩人にとって、よるべなき魂の悲しい漂泊者の歌を意味するのだ。
誰れか軍隊の凱歌と共に、勇ましい進軍喇叭で歌はれようか。かの声を大きくして、僕等に国粋主義の号令をかける者よ。暫く我が静かなる周囲を去れ。 「日本への回帰」というエッセイは、その題名からして非常に誤解を招くものである。
つまり「回帰」という言葉が引っかかるのだ。朔太郎が言いたいことは、「漂泊者」と「日本的なるものへ回帰すること」がイコールなのではない。
あくまでも漂泊者の歌う「歌」が、「日本的なるもの」なのである。 朝日新聞の津村氏に電話で強制的にたのまれ、気が弱くて断り切れず、とうとう大へんな物を引き受けてしまった。
(中略)とにかくこんな無良心な仕事をしたのは僕としては生まれて始めての事。西条八十の仲間になったうで、懺悔の至りに耐へない。 だが朔太郎の仕事が時局への順応に見えたのは、やはり仕方のないことだった。そして昭和十四年九月、第八詩集『宿命』を刊行する。 その中の新作品「物みな歳月と共に亡び行く」は、昭和十二年二月に前橋に帰郷した折りに「郷土望景詩」に歌った場所を取材している。 物みな歳月と共に亡び行く―郷土望景詩に歌ったすべての古蹟が、殆ど皆跡方もなく廃滅して、
再度まだ若かった日の記憶を、郷土に見ることができないので、心寂寞の情にさしぐんだのである。 かつて古い日本の象徴として「田舎」という言葉で憎んだ郷土も今は見る影もない。そして同時に朔太郎自らも年老いてしまった。 悲しき帰郷者!我等はその行くべき所を知らず、泊まるべき家を持たない。 「漂泊者」がいつの間にか「帰郷者」に変わっているのだ。だが、この帰郷はあくまでも漂泊の中でのことなのである。 それは、ほとんど同時に刊行されたアフォリズム集『港にて』の「自序」と並べて見ると分かる。 書名を「港にて」と題したのは、この書が私にとっての休息であり、航海の終った日を記念するからである。(中略)
とにかく私は、荒天の日の航海から、一先づ港に入った思ひがして居る。何時また私は新しい出帆をするかも知れない。
だがその風を待っている間、私はこの「港にて」休息しながら、次の航海を待機しよう。 そして朔太郎最後の著書は、昭和十五年十月刊行のエッセイ集『阿帯』である。その題名の意味は「白痴者」であるという。 こんな文学をする以外に能もなく、無為に人生の定年を過ごした私は、まさしく白痴者にちがいない。 極めて自嘲的である。そして昭和十六年秋頃から肉体の変調を感じ、昭和十七年四月頃から病状はとみに悪化し、肺炎の為に五月十一日、遂に永眠する。享年五十七歳だった。 |
|
|
|
萩原朔太郎論
|
 |
|
|
|
(1)まとめ 「はじめに」で、テーマを「故郷への愛憎という相反した感情が、彼の作品にどのように影響したか、また何故そのような感情を持たねばならなかったか」とした。
朔太郎のいう故郷とは、単に郷土前橋を示すものではない。それとは別に、魂の故郷を示している。 つまり朔太郎の場合、郷土が魂の故郷となり得なかったのだ。ここに朔太郎の不幸の原因があった。 前進している間はいい。(中略)やがてあらわれるであろう「絶対」の姿を期待している間はいい。
しかし陸地とは、ついに幻影であり、(中略)どこにも信用のおける足場といってなく、幻影から幻影へと彷徨しているうちに、
ともすると人は、最初に捨ててきた古い世界の地盤がいちばん、しっかりしていたのではないかというような不甲斐ない錯覚におそわれはじめる。
かれは引き返す。だが、引き返したら最後だ。(中略)復讐の機会をうかがっていた時間が、このときとばかり、猛然とかれに躍りかかる。
(中略)いまさら年をとったと嘆いたところで駄目であり、海亀にのって出発した我々の昔話の主人公は、
故郷の風物が一変し、誰ひとり、かれを見知っている人間のいないことに気づくのだ。 まさに朔太郎の運命そのものをよく言い表している。「架空の世界」が発表されたのが、昭和十六年十一月だから、朔太郎の死去する半年前である。
だからこのエッセイは、(コロンブスのことを題材に書いたものだが)言外に朔太郎を含む日本浪漫派に対して揶揄しているのかも知れない。 近代のドンキホーテは、ずっと懐疑的の性格であり、宿屋の女中を女中と知って、
自らその虚妄の中に幻住し、情熱の破綻を意識して居るからである。 (2)朔太郎を通して考えること 萩原朔太郎は、その作品によって随分印象が違う。「月に吠える」「青猫」の口語自由詩にみられる病的なまでのイメージの繊細さ。 ボードレールのような都会や群衆を歌った詩。「氷島」の激しい文語調による漂泊者の悲痛な詩。小説「猫町」のような幻想とユーモア。
ニーチェを連想させるアフォリズム。徹底した二元論に捕らわれた(あるいは引き裂かれた)詩論や文明論。音楽や写真、映画など当時のモダンな趣味に関するエッセイ、などなど。 [参考文献] |